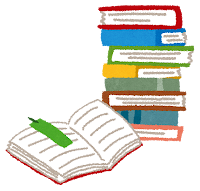5/20-26までに出版される本、約1200冊から個人的に気になった本を約100冊くらい選抜しました。
◆ビジネス・ノウハウ
各業界のトップを走る21企業・団体の代表者が描くビジョン!VUCA時代の今だからこそ、明確なビジョンを描き、新たな事業に取り組む。様々な困難や危機に対峙している経営者・ビジネスパーソンへ、明日への指針。
パーパスとは、企業の「存在意義」「志」「使命」のことで、一般用語では経営理念と言われます。現在、社長の心構え的な経営理念から、「わたくしたち」が社会にどのような貢献をするのかというパーパスへ多くの企業で進んでいます。一方、パーパスは一時的に「流行った」「作った」、でも「使えない」という企業も増えています。本書では、「アンバサダー」という浸透・普及の代表者を任命し、彼ら主導の「つまどう会議」(つまりどういうこと会議)という手法でパーパスの解像度を上げ、浸透させ、職場を、文化を変えていく方法について、考え方から実際の浸透ワークショップの実施の仕方まで解説します。 パーパスを社内に浸透させたい企業にとって、その具体的な道筋と方法を示した“役に立つ”本です。
生成AIに代表されるような、技術の加速度的な進展で私たちの仕事や生活は一変しようとしている。そんな不確実性がます社会、私たちはどのように前を向いて歩き続ければよいのか。インターネット黎明期に起業し、現在も実業家として挑戦し続ける著者が練り上げた、自己鍛錬・対人論・組織マネジメントを体系化したビジネス哲学決定版!
この本を手に取ってくださって、ありがとうございます。あなたは、きっと本が大好きな方か出版界の関係者なのでしょうね。そんなあなたは、日本から街の本屋が消える日が想像できますか?なぜ今、街から本屋が消えていっているのだと思われますか?この問いに対して著者の私が「本屋を殺す犯人を突き止める」訳ではありません。「出版社に原因がある」「本屋に責任がある」「取次が悪い」「読者の活字離れ」、それぞれ少しずつ当たっていても一面的です。本屋が消えつつある理由は、そんなに単純なものではないのでしょう。この答えを出すために日本初の試みとして出版界のプロフェッショナル達が実名(一部匿名)で、それぞれの立場で本屋について熱く本音を語ってくれました。読者のあなたと一緒に出版界の現状を俯瞰(ふかん)しながら、問いの答えに近づいてゆこうと思っています。この本を読み終える頃には、本屋が消え続ける理由も分かり、一方では本屋の明るい未来への希望も感じ取ることができるでしょう。ようこそ、出版流通という名のラビリンス(迷宮)へ!
忙しい毎日を過ごしている現代人にとって、「せっかちに行動すること」は理に適っている――本書は、せっかち力を駆使して仕事と信頼を獲得してきた著者による、せっかちな性格を活かしながら、効率よく、効果的に仕事をするための方法をまとめた本です。
「面白かった」「やばい」しか出てこない人でも、書きたいことがとめどなく溢れてくる!!
P&Gでマーケティングを学び、その後DeNAで100人規模のマーケティング組織を率い、独立後は100社以上の売上成長を支援してきた実務家が、「最強ブランド」のつくり方を指南!鍵となるのは、「UAV(ユニーク・アトラクティブ・バリュー、顧客に選ばれ続ける価値)」という新キーワード。本書では、「自社の強み」と、「顧客インサイトの理解」を掛け合わせることで、他社に模倣されにくい価値をつくりあげるフレームワークを解説していきます。
◆政治・経済・社会
大統領選挙の仕組みから今後の課題まで、現代の米大統領に関する広汎な事項を扱う。大統領の動きを追うことで、過去を振り返り未来を見据える手掛かりとなる。
ある貴族の家系を、フランス革命、帝国主義、ふたつの世界大戦、戦後の高度成長期、そして1980年代の保守革命から、格差が拡大する現代までたどり、その8世代の人々が直面した富と社会の変貌から、こうした格差の謎にせまる。不平等の歴史的変化を理論的に分析してきた世界的権威の仕事を、わかりやすく理解できる入門書。
コロナ・パンデミック、世界戦争の予兆――。世界秩序は急速に流動化し、グローバル・サウスといわれるアジア、アフリカ、中南米の新興国群をはじめ、「全員参加型秩序」の新潮流が動き出している。経済産業とインテリジェンスの最前線を生きた著者が、二一世紀システムの創造的参画者として日本が進むべき道を考察する。
2023年10月1日、インボイス制度が開始されました。実はこのインボイス、百害あって一利なしの制度です。会社だけでなく、社会で働くわたしたち全てに関係しています。この制度に反対して、大きな市民運動、「STOP!インボイス」も起こりましたが、大手メディアからは黙殺され、ほとんどの人はその実態を知らぬまま、導入が強行されてしまいました。本書は、約2年間にわたって反対運動の現場に密着し、自らも問題点を指摘し続けた筆者が、その経緯を振り返りながらこの制度の問題について指摘、分かりやすく解説します。
日本の漁業の生産量・生産額はこの30年減り続けている。魚の消費量もこの20年右肩下がりだ。漁業の未来への活路はあるのか。
共同通信の好評連載「迷い道」を書籍化。家族との葛藤、仕事の失敗、病気の苦悩、親しい人との別れ、挫折……。私たちの身近にいるごく普通の人々が様々な生きづらさと向き合い、回り道の人生を歩んできた姿を描く。迷いを抱えながら生きる人への共感とエールを込めた一冊。
学校じゃ教えてくれない、お金の「稼ぎ方」・「増やし方」の教科書。※説明少ないですが、目次から面白そうという判断しました。
中東情勢/ウクライナ侵攻/中国経済危機……独裁化するマッドマンたちのフェイク情報を見破れ!マッキンゼー伝説のコンサルタントが、混迷する世界情勢を誰よりもわかりやすく分析!
AI時代の世界覇権の行方を左右するもの、それはデータ、計算、人材、機構の4つの戦場だ――。前著『無人の兵団』でロボット兵器の実態をスクープした著者が、「知能」を持つ自律兵器やサイバー戦など、戦略資源としてのAIをめぐる暗闘の実情を炙り出す。
日本は本当に右傾化したのか? 20年余りの政権運営から見えてくるものは――。読売新聞政治記者が、政局の裏側を読み解く。
権威主義体制が長く続いた台湾。1996年に総統の直接選挙が始まり、2000年には国民党から民進党への政権交代が実現した。今や「民主主義指数」でアジア首位に立つ。中国の圧力に晒されながら、なぜ台湾の民主主義は強靭なのか。また弱点はどこにあるか。白熱する選挙キャンペーン、特異なメディア環境、多様な言語と文化の複雑さ、そしてあらゆる点で大きな影響を及ぼすアメリカとの関係に注目し、実態を解き明かす。
コロナ禍、ウクライナ危機を経てインフレ転換した世界経済。有事対応で財政出動を繰り返した日本は、債務残高対GDP比で先進国最悪である。デフレ下でこそ持ちこたえられた財政には新たな破綻シナリオもよぎる。日本の危機的状況を再確認するとともに、立て直しの方策として、税制と財政ルールの改革、成長戦略、セーフティネット構築、ワイズスペンディングなど5つを提言。未来につなぐ財政民主主義のあり方を問う。
何をやっても人生が好転していかない?だけど、あなたは何も悪くなかった!キーワードは【罪悪感】じつは思考の99%が無意識下にある「潜在意識」。思考が現実化する″仕組みとともに「潜在意識」の見直しに取り組めば叶えたい願望が現実にやってくる。
今の世の中は、VUCA時代〈Volatility(変動性)・Uncertainty(不確実性)・Complexity(複雑性)・Ambiguity(曖昧性)〉と言われており、私たちをとりまく「常識」は常に変化しています。ときには、白だったものが黒になるほどの極端な変化をすることもあります。もしも考え方をアップデートできないまま、社会の変化に取り残されてしまったら、単なる「時代遅れ」ではすまされないほどのダメージが出てしまうでしょう。これからは、自分で考え、行動する姿勢が今まで以上に必要になってきます。そのために必要なのが、本書で紹介する「疑う思考」です。
アメリカにおける公立学校民営化の推進、犯罪の厳罰化により膨らみ続ける刑務所人口、移民取り締まりの強化……。これらの現象の背景には世界的な企業の利益追求の思惑がある。オバマ政権下で教育改革に関わった著者がデータや事例をもとに、人種差別・不平等の助長がビル・ゲイツ、マーク・ザッカーバーグ、ウォルトン一族などの超富裕層の利益へとつながる「戦略的レイシズム」の存在を暴き、格差社会のメカニズムに迫る。
「米国一強」崩壊後、日本はどうすべきか? 米中の拮抗、G7主導体制の後退、権威主義や独裁国家の台頭、ウクライナやパレスチナの戦争、影響力を増すグローバルサウス――「自由・民主主義・法の支配」が脅かされる危機の時代に、日本が採るべき道と果たすべき役割は何か? 国連・JICAでの経験を通じて世界の現実を見た国際政治学者が提唱する地政学的思考!
新紙幣の顔、渋沢栄一のひ孫が提案する資本主義の未来とは?「日本近代資本主義の父」として、2024年には新一万円札の顔となる渋沢栄一。しかし、今私たちの日常に浸透している資本主義は、栄一が実現しようとした資本主義=合本主義とは、大きく異なるものだった――。世界・日本各地で環境・地域づくりを行ってきた「里山資本主義」のパイオニアである著者が、曾祖父・栄一が目指した資本主義を検証しながら、これからの時代の自然と経済生活、未来の資本主義のあり方を提示し、名著『論語と算盤』を現代にアップデートする。
現在のペースだと男女間の賃金格差を解消するためには257年かかる――。257年待っていられないすべての人へ。お金×ジェンダーの必読書。もし、自分が一生、男性よりも収入が少ないと知っていたら?今日、女性であることはそうなる可能性が高いことを意味し、男女の間にはいまだに大きな格差が存在している。「女性の賃金を低くするのは違法だから賃金差別は存在しない」「賃金格差は教育で解決できる」などの通説を覆しながら、格差が生まれる根本と平等に向けた具体策に迫る。
◆エッセイ系・紀行・旅行記
韓国で20万部のベストセラー。IVE、IU、SHINeeなど多数のアーティストの作詞を手掛けた、キム・イナ。待望の日本訳。「先の見えないありふれた日常を生き疲れないために、まるで「そう、それでいいんだよ」と耳元で囁いてくれるような、言葉のプロが紡ぐ「魔法の言葉」たちに癒される。」※恐らく、エッセイのような内容。
自由に気ままに、自分の気持ち次第で動けるのが「ひとり旅」の醍醐味。ひとりならまわりを気にせず、「初めて」のことにもたくさん挑戦できる。ざっくりと目的を決めて、あとは気の向くまま。ノリと感覚を大事にする旅は、大人にこそおススメだ。女性向けエッセイの第一人者が、日常から解き放たれた国内外の場所で得たさまざまな気づきと経験を紹介。旅の前に押さえておきたいスケジュールの立て方、安全対策、オススメの持ち物など、お役立ち情報もたっぷり披露!
―アポロ11号が月面着陸をしたその年、16歳の私もまた旅に出た。両親に気づかれないよう、早朝5時にこっそり自宅を出て、ひとり旅に出た高校2年の春。約一週間後に帰宅すると、心配した両親や先生たちからこっぴどく叱られたものの、そこから根無し草の「ひとり旅」人生が始まります。ヒッチハイクで福岡の自宅から青森まで向かった初めてのひとり旅を皮切りに、ホンダのNⅢで5500キロを単独走破した16日間の自動車旅、そして年齢を重ねたからこそ味わい深い、ローカルな風景やグルメを楽しむのんびり旅など、10代の頃からひとり旅をこよなく愛する著者のユーモア溢れる旅の記録集
『弱虫ペダル』渡辺航 推薦!!夏のフランスは華やかでおもてなしも上手だ。生活の横をレースが通過する!愉しく感動的な旅行記。美しい田舎町を駆け抜ける選手たち、道端で出会うヴァカンス中の人びとの熱狂──食、宿、自然etc…普通のガイドブックには載らない、フランスの原風景を体験できる“特別な3週間”の道しるべ。
私にとってカメラを持つことの最大の効用は、世界に「つまらない場所」というのが存在しなくなったことであるーー。ブッダガヤで出会った「瞳の少女」、ヘルシンキで胸を熱くした幼き兄妹の姿、夜のコルドバで心を騒がせた「路地裏の哀愁」……。沢木耕太郎が旅先で撮った八十一枚の写真と、その情景から想起する人生の機微を描いた短いエッセイ。大人気フォトエッセイ『旅の窓』、待望の続編。
80代から90代の大台へと足を踏み入れた作家がつづる、老いの日々。少しずつ縮む散歩の距離、少量の水にむせる苦しさ、朝ぼんやりと過ごす時間の感覚など、自身に起きる変化を見つめる。一方、年長者が背筋を伸ばしてスピーチを聞く姿に爽快感を覚え、電車の乗客の「スマホ率」など新たな発見も。「ファックス止り」の自分をなぐさめ、暗証番号を忘れて途方に暮れて……。老いと向き合い見えたこと、考えたこと。
いつまでも迷子であり続ける人のための手帳です。これ一冊あれば、貴方もきっと迷子になれる。「いつもインコを肩にのせている神秘的な少年」になろう、と考えたのだ。ぎゃー。何なんだ、それ。よせ。やめろ。でも、夢見る私はもう止まらない。ピーコちゃんを肩にのせて、おそるおそる玄関のドアを開けてみた。(本書より)「北海道新聞」好評連載ほか、人気歌人の最新エッセイ全57篇。
「この社会は女性たちに、あまりにも長い間、あまりにも厳しく妻として、母親として生きることのみに意味を与えてきた――」世界トップの少子化が進み、独身税の導入までささやかれている韓国。そんな社会で、かつて結婚に憧れた著者は一人で生きる選択をする。カウンセラーとして働き、自分の時間を過ごす中で、内なる声に耳を傾けることが大切だと気づく。非婚女性たちにやさしく寄り添う温かいエッセイ。
精神科医として約10年、つねに頭をフル稼働させて格闘する日々を送る著者。「予期せぬこと、焦ること、絶体絶命のピンチになること」であふれている現場で、著者は隠しきれない生身の自分を抱えながら試行錯誤する。「切り捨ててしまったかもしれない部分をもう一度検討し直せる〝倫理的なサイコパス〟に私はなりたい――」H氏賞受賞の詩人としても活躍する医師による、ユーモラスで大まじめな臨床エッセイ。
こんなへんてこりんでおもしろい職業ってないかも!現役書店員さんが、さまざまな悩みを抱えてやってくるお客様に、ぴったりの本をすすめまくる、笑いあり涙ありの本屋エッセイ!今からすぐ本屋さんに行きたくなります!
1年かけて巡った47都道府県の旅情報チャンネル登録者数177万人超えのYouTuberエミリンが、1年かけて回った47都道府県の記録を一冊にまとめた旅エッセイ。
◆ネイチャー・研究系
地球上の生命はみな、単独では生きてゆけない。動物と植物の持ちつ持たれつの関係や、驚きの生存戦略、進化と生態系をめぐる複雑な仕組みを、最先端の研究を踏まえ、時に皮肉も交え軽妙な筆致で綴る。トリビア満載、ユーモア満点。視野の広さと確かな知見に基づく、生きものと科学への愛に溢れたエッセイ集。カラー図版あり。
「漫画と社会を接続する B.E.」はZINE(同人誌)として過去に2号発行されておりましたが、本3号よりリニューアル号として出版いたします。「動物と植物」をテーマに、日本のヴィーガニズム・動物倫理の現状をまとめています。下敷きにしたのが漫画『ダーウィン事変』(うめざわしゅん、講談社)、『フールナイト』(安田佳澄、小学館)です。
「無」という言葉には,どこか心を引きつけるものがあるのではないでしょうか。本書は,そんな魅力的な響きをもつ「無」を追求する一冊です。まず取り上げるのが,数の無といえる「ゼロ」。その発見から成立までには長い歴史がありました。つづいては「真空」について。現代物理学によれば,真空はただの「空っぽの空間」などではないといいます。さらに,最先端の理論物理学では,空間や時間さえ存在しない「究極の無」にもせまろうとしています。無の探究の歴史は,物理学の発展の歴史そのものでもあるのです。私たちの住む「有」の世界を鮮明にえがきだす「無」。そのおどろくべき正体に,じっくりとせまっていきましょう。
◆評伝・批評・評論
10年間、あなたの代わりに読んできました。話題書150冊の「肝の1文」を並べてみたら、いまの日本に至るまで、10年間の進歩、退歩、あし踏みが見えてくる。
心療内科医として多くの人々と向き合ってきた著者が、長年の経験と医学的知見をもとに、幸福な人の条件、人間関係、歳の重ね方をアドバイス。すいすい読めて、心がすっと軽くなる。著者自身も実践する、幸せを呼び込む習慣と、しなやかで心豊かに生きるヒントを紹介する。
鄭秋迪は、関東学院大学で「吉本ばなな」について中国での論文やネットと独自のアンケート調査から「中国で「吉本ばなな」はどのように受け入れられているか」を研究、ばなな独自の「好きっていう場」「半独語」「即非の文学」などを分析し、ばなな文学の本質に迫る。
特集1: 「反戦」と仕事特集2:住まい、どうですか?
「あれはいったい何だったのだろう――?」過去の人生において遭遇した、明確な恐怖とは言いがたい、けれど忘れることのできない記憶や小説。大ヒット作『恐怖の正体』(中公新書)で話題を呼んだ作家・精神科医である著者が、精神の根源に触れるそうした〈恐怖寸前〉の〈無意味で不気味なものたち〉に惹かれて渉猟した、異色の文学エッセイにして読書案内。
いまの日本人に一番足りないものは何だろうか?本書では、“モヤモヤを抱えた編集者との往復書簡”によって、内田樹が「勇気」の意味を考察します。ジョブズ、フロイト、孔子、伊丹万作、河竹黙阿弥、大瀧詠一、パルメニデス、富永仲基……思いがけない方向に転がり続けた二人のやりとりは、結論にたどり着くことができるのか。読み終わる頃には、あなたの心はフッと軽くなってるに違いありません。
最近「ぼうけん」してる? 思わず答えにつまったあなたに、この本を贈ります。立川のPLAY! MUSEUMで開かれた「エルマーのぼうけん」展で、冒険をめぐるたくさんの本を集めて「ぼうけん図書館」をつくったら、大人から子どもまでが夢中になる、大人気のコーナーとなりました。そこで、ぼうけんが大好きなエルマーの力を借りて、もっとぼうけんしようよ! そう呼びかける本をつくりました。心躍る冒険、ちょっぴりせつない冒険、汗だくの冒険、じっと考える冒険、特別な冒険、日常を生きるという冒険。物語のなかで主人公たちは、その冒険が大きくても小さくても、うまくいってもいかなくても、それぞれのやり方で自分の世界を広げていきます。勇気をもらい、元気をもらえる「冒険」をキーワードに、絵本、童話、児童文学から一生ものの100冊を集めました。子どもと、かつて子どもだったすべての人たちへ、あなたのなかの冒険心をやさしく、ときどきはげしく揺さぶる「冒険」をエルマーと一緒に見つけに行きませんか。
◆技術・デザイン・芸術
詳しい本の情報は書かれていませんが、これからの時代、酷暑が大変なので、これらの情報は気になる。
特集「特撮の現在 研究と文化の隣接点」
システムズエンジニアリングの名著、認定システムズエンジニアによる翻訳本がついに登場!システムズエンジニアリングの専門家であるジョン・ホルト教授の著書『Systems Engineering Demystified』(第2版)の日本語版が『システムズエンジニアリングの探求』としてリリースされました!
計事務所に「つくる」要素を組み込む、自らが暮らす地域を楽しくつくり変える、目の前にある材料を掘り起こす、これからの建築の担い手を育てる。多様な「つくる」を展開する人たちが、生い立ちから仕事、活動を語る。設計して終わりではない時代に、新しい領域でどんな働き方をするのか。可能性を探るきっかけとなる一冊。
アーティスト、ギャラリストたちが語るリアルなアートシーンロンドン、東京、ベルリン、アムステルダム4都市の注目アーティスト / アート最新情報東京を代表するギャラリストたちが語る、アートの現在
◆ゲーム関連
真面目で素直な英川叡子と、寡黙で謎の多い美原美子…。最初こそ対抗意識を燃やしていた2人だけれど、レトロゲームの話をするたびに少しずつ心の距離は近づいてーー!?レトロゲに導かれ、その魅力にハマった2人の高校生が、ゲーム画面の中にある”無限の世界”に飛び込んでゆく…!!懐かしくて新しい、青春レトロゲームコミック第2巻!!
ハイチ移民の子として生まれたアメリカ任天堂の元社長兼COOのレジー・フィサメィが35年のキャリアで学んだ教訓と哲学とは?・自分の考えを貫く勇気を持つ方法とは?・絶え間ない好奇心を持ち続ける方法とは?・業界のトップに立つために必要な方法とは?・現状を打破するタイミングを見極める方法とは?P&G、ペプシコ、VH1などでキャリアを積み、アメリカ任天堂のトップまで上り詰めた男のキャリアを通じて直面した困難を打破し、ゲーム産業史上最もパワフルな人物の一人になるまでの激動の人生。
◆文学・小説
映像や3DCGを扱う制作プロダクションに勤めるうつヰの一日は長い。今夜バスタオルで体を拭くのを忘れないようメモするアプリケーションには何が最適か。部長の言うユーキューは「有給」なのか「有休」なのか?仕事を終えると「プリンセサイザ」にログインする。京王線沿線の各駅に配置された王女たちと、仮想空間システムを渡り歩けるソーシャルVRの中で交流するのだ。選考会で激賞された第5回ことばと新人賞受賞作「フルトラッキング・プリンセサイザ」ほか、一年後をつづった「メンブレン・プロンプタ」、うつヰの学生時代を描いた「チェンジインボイス」を収録。
中学生のヘイゼル・ヒルは地味な女の子だけど、スピーチコンテストで優勝を目指していた。クラスでたった一人の話し相手は、タイラーというおしゃべりな男の子。でも、話の内容は、女の子のことばかり。最近、人気者のエラ・クインにふられた腹いせに、彼女の悪口を言いふらしている。昨年のスピーチコンテストで優勝したエラは、ヘイゼルの宿敵だった。でもタイラーが、エラのSNSアカウントにセクハラ的なコメントを書き込んでいると知って、ヘイゼルは毅然として立ち向かう。ハラスメント、LGBTQ、SNS問題など現代的なテーマを扱ったYA小説。
おのれを「正常」だと信じ続ける強制収容所の司令官、司令官の妻と不倫する将校、死体処理班として生き延びるユダヤ人。おぞましい殺戮を前に露わになる人間の本質を、英国を代表する作家が皮肉とともに描いた傑作。2024年アカデミー賞国際長編映画賞受賞原作。
進行していく温暖化と、世界各地で相次ぐ戦 乱。われわれは地球と共に生きていく資格が あるのか?――22人のSF作家が考察する。
シャーロック・ホームズはここから始まった? 幻のデビュー作「ササッサ谷の怪」から、ストランド・マガジン最後の掲載作品「最後の手段」まで。ミステリーのみに留まらない希代のストーリーテラー、ドイルの魅力を再発見する名短篇全十四編を収録。
田畑書店「ポケットアンソロジー」シリーズと連動する季刊ベース誌の第7弾!今号の特集は山川方夫。およそ60年前に34歳で交通事故により急逝。今も根強い読者がいる伝説の作家の新しさを解明する。また、〈文豪とアルケミスト〉とポケットアンソロジーのコラボにちなみ、徳田秋声研究の第一人者、大木志門氏に学会発表の一端をご寄稿いただいた。
◆コミック
存在しないはずの本を買ってしまう「継ぎ穂」、空中散歩を楽しむ「21gの冒険」、異国のラジオが聴こえ始める「混信」、図書館の地下に迷い込む「地下図書館探検譚」。日常から地続きの〈不思議な世界〉に読者をいざなう、極上のローファンタジー4編を収録。ネットやCOMITIAで大注目の才能による商業デビュー単行本。
◆競馬
ロングセラーとなった「馬場のすべて教えます」の続編。JRA全10場の馬場解析を中心に、馬券につながるヒントを解説するほか近年、情報開示となった含水率・クッション値などのポイントも紹介。「JRA馬場土木課」の協力のもと、「今後、馬場はどうなるのか」と題し、JRAトップジョッキー(川田将雅騎手・藤岡佑介騎手・坂井瑠星騎手)&馬場土木課座談会の模様を掲載。JRAだけでなく地方競馬場に広がる〝白い砂〟の正体にも迫る。単に競馬予想に活かす馬場本ではなく、馬場の奥深さを伝え、初心者からマニアまでを満足させるような、これまでにない‘馬場の参考書’の新作。
◆その他(歴史系とか哲学系とか)
地の果てまで追い詰めると戦勝国が誓ったナチ戦犯。だが戦後早々、西独、CIAや西側情報機関で元ナチは重用された。冷戦期、元ナチ残党が世界で引き起こした混乱の実態をモサド未公開史料、元スパイへのインタビューなどから描き出す。
帝国日本の出版市場は合法/非合法を問わず、植民地の人々を積極的に読者として包摂しようとした。朝鮮人にとって日本語は抑圧する言語であり、抵抗の思想を学ぶための言語であり、娯楽のための言語でもあった。『戦旗』や『キング』、マルクスやレーニン、金子文子や火野葦平、林芙美子らの思考や文学が、発禁本とともに帝国の支配圏でいかなる思想や文化を醸成したのか、多彩な作品から読み解く。
たとえば紀貫之によると伝えられている「高野切」は、書を学ぶ人の手本となる書である。この名品には書き間違いがあるといわれ続けてきたが、しかしそれは本当に誤字脱字なのか。著者は実作者の目をもって書と対話し、ひらがなという大河の最初の一滴にさかのぼる。「つながる」という本質に注目しながら、美の宇宙を読みくこころみ。
世界でいちばんやさしい哲学をコミックで読む!ある日、少女ソフィーのもとに届いた差出人不明の1通の手紙。そこにはたったひとこと「あなたはだれ?」とだけ書かれていた。それは「哲学」への招待状だった。世界的ベストセラーの哲学ファンタジーがフランスの人気作家によるコミック、バンドデシネになってオールカラーで登場!
デカルト『方法序説』、カント『純粋理性批判』など、世の偉大な哲学者たちが著した名著の数々。哲学者の名前と書名を見れば、おのずと知的好奇心が湧いてくるものだが、いずれも分厚く難解で、読み通すのはなかなか難しい。そこで本書は、哲学分野における名著50作品の要点を図版も使いながら整理し、そう簡単に読み解くことができない哲学書の内容を読者にわかりやすく伝える一冊。
人間とはいかなる存在か? 動物やAIは? そして社会はどこへ向かうのか? 初出6本を含む白熱の対論12本、全608頁!哲学、倫理学、社会学、経済学、宇宙開発、ロボット工学、文芸批評、文化研究、SF、ファンタジー、コミック、アニメーション──現代日本が誇る不世出の社会哲学者・稲葉振一郎の膨大な仕事、広大な関心領域を一望のもとに収めた初の対談集。大屋雄裕、吉川浩満、岸政彦、田上孝一、飛浩隆、八代嘉美、小山田和仁、大澤博隆、柴田勝家、松崎有理、長谷敏司、三浦俊彦、河野真太郎、金子良事、梶谷懐、荒木優太、矢野利裕と第一線で活躍する作家、批評家、研究者を迎えて縦横無尽に語り尽くす。